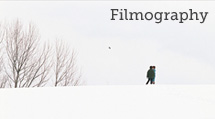切断せよ、と彼女は言った
鏡・空間・ソニマージュ ― 七里圭の摩訶不思議な映画/音楽世界 (桑野 仁)
「映画としての音楽」解説文(パンフレットより)
桑野 仁
1965年生まれ。映画評論家。共著にE/Mブックス・シリーズや『ロバート・アルドリッチ大全』(国書刊行会)など解説多数。
2014年4月26日、渋谷のUPLINKで行われた、何とも風変わりで、一体これを何と呼ぶべきか、にわかには名状しがたい実験的なライブ・イベント。それは、ただの“映画”ではなく、“音楽”でもなく、そして“演劇”でもなく、あくまで“映画としての音楽”。作者の七里圭自身の説明によれば、「それは、実演され、空間に拡張されたサウンドトラック」であり、「スクリーンという窓のある部屋にいる/いない12人の歌、謡、語り、叫びが、映し出される指示に従って冷徹に進行し怒号のように渦巻いた」。
スクリーンに映し出される、先に別撮りされた映像と対峙するようにして、12人のボイス・パフォーマーたちが、時に囁くように、また時には呻き叫び、あるいは歌や読経のように抑揚をつけて台詞を読みあげては、画面に音入れをしていく様子を、筆者を含め、当日、会場を埋め尽くした観客=聴衆は、前方のスクリーンと後方にいるパフォーマーたちを視野の両端に置く形で側面に設えられた座席に腰を据え、不自由さを強いられて半ば身を引き裂かれる思いを味わいながら、代わる代わる見つめ、聴くこととなったのだった。
「空間全体を、ある意味で映画として考えるといいますか、エクスパンデッド・シネマ、拡張映画っていう分野がありますけども、拡張映画をさらに拡張するというような。拡張映画って、スクリーンの枠を超えて映像を広げてく作品のジャンルですけど、それを僕なりに考えてみて、空間全体が映画で、映画の中にいるみたいにしたらどうなのかなって…」と、後日行われた対談の中で、七里監督自身がこの企画を考え付いた当初の構想について語っているが、そう、確かにあの日あの時、UPLINKの会場は、通常の映画上映会場とは次元の違う異空間へと変貌を遂げていた。
さてしかし、この『映画としての音楽』は、それぞれ別箇に構築された音と映像が、スクリーン上で予定調和的に幸福に結びついて作品が無事完結し、めでたし、めでたし…で終わる、お気楽で能天気な作品などでは、まったくない。七里圭という作者、どうやら“のんき”を自らの売りにしているようだが、実はどうしてなかなかの食わせ者で、相当ひねくれていて頑固な性格の持ち主であることは、既に彼の作品を目にしている者ならば、直ちに了解できる通りだ。
従来のものとは異なる音(son)と映像(image)の結びつきの新たな可能性を問い直すべく、かのジャン=リュック・ゴダールが唱えた“ソニマージュ(sonimage)”の方法論、あるいはまた、マルグリット・デュラスによる別種の試みを独自に受け継ぐ形で、七里監督はこれまでにも自作においてさまざまな実験的試行を繰り広げてきた。なかでもやはり、『眠り姫』の映画作りが、この『映画としての音楽』とは正反対に、まずは台詞の収録から先行して始まり、対話劇としての構成が整えられた後、画面にはほとんど人物が登場しないあの何とも不思議な風景の撮影や、優美きわまりない音楽が、それを追いかける形で組み立てられていったというユニークな製作経緯が、ここでただちに想起される。その一方で、数度の改訂作業を経て一応の完成を見たはずのこの『眠り姫』は、その後もさらなる進化=深化を続け、音楽の生演奏による上映会や、アクースモニウムなる多次元立体音響システムを駆使し、自己統一性がゆらいだヒロインの失調感覚をよりリアルに体感させる特別上映会、はてはなんと、会場を真っ暗闇にして映画の画面は一切映さず、そのサウンドトラックのみを観客、いな聴衆に味わってもらう(!)という空前絶後の上映の試みまでなされてきた。
建築家・鈴木了二との共同監督作である『DUBHOUSE:物質試行52』も、「建築は、闇を作る力がある」という彼の言葉を引用した冒頭の一文紹介の後、ほとんど暗闇の中に沈んだ黒画面が8分間にわたって続き、観客に何やらただならぬ切迫した緊張感をもたらすことになる(実はその深い闇の奥に一体何が秘められ、また、本来35ミリ・フィルムで撮影されたそのプリントがデジタル化されることによって、そこに一体どんな決定的な変化が生じるか―それこそが七里監督による今回の連続講座の議論の最大の焦点のひとつであり、彼自身が熱を込めて大いに語っているところでもあるので、そちらをぜひ参照してもらうことにして、ここでは委細は省略)。と同時に、この作品の後半の8分間では、前半の闇とシンメトリックな対を成すように、鈴木のインスタレーションを鮮やかな光と共に闇から浮き上がらせるショットが繰り広げられ、闇と光をいわば合わせ鏡のようにして向き合わせ、一つに閉じることで、この特異な短編記録映画は厳密に設計されていた。
こうした数々の実験的試みを経たうえで生み出された本作は、その方向性をさらにいっそう過激に推し進め、大胆不敵で挑戦的とさえいえる前衛的手法が用いられている。
この『映画としての音楽』本編の骨格を成す物語の題材として、七里監督は、オスカー・ワイルド原作の戯曲「サロメ」、そしてそれを神韻縹渺たる典雅な日本語に移し替えた日夏耿之介の訳文をテクストに選び出した。サロメといえば、義父たる国王の求めに応じて妖艶な踊りを披露し、その褒美に洗礼者ヨハネの斬首を求めた古代ユダヤの伝説的王女として、古来よりさまざまな芸術家たちの感興と想像力をかきたて、とりわけ19世紀末のヨーロッパにおいて、このサロメを題材に、ギュスターヴ・モローの絵画や、それを作中で絶賛したユイスマンスの小説「さかしま」をはじめ、マラルメやフローベールの詩劇や短編、あるいはワイルドの戯曲に付されたビアズリーの挿絵、等々、世紀末芸術の精華というべき多種多様な名作が生み出されたことで有名。その後、20世紀に入ると、オペラや映画などにも幅広く転用されており、サイレント時代からの幾度にもわたる映画化の試みに加え、サロメの踊りの場面を大胆に劇中に採り入れた『ラスト・ダイビング』という異色作が、ポルトガルの異才ジョアン・セザール・モンテイロの手によって撮られてもいる。
七里監督は先にも、『のんきな姉さん』では、山本直樹の同名コミックを直接的な原作に仰ぎつつ、その山本作品の着想の源泉たる森鴎外の名作「山椒大夫」と、同じくこれに想を得た唐十郎の小説「安寿子の靴」を、そしてまた、『眠り姫』でもやはり、山本直樹の同名コミックを原作にしつつ、その山本作品が下敷きにした内田百閒の短編「山高帽子」を、巧みに作中の要素に採り入れており、そうした重層的なインターテクスチュアリティ(引用の織物!)への志向=嗜好を窺い知ることができる。
けれども、この『映画としての音楽』は、いざ本編が始まっても、サロメや国王、ヨハネといった人物たちは一向に画面に登場せず(またしても!)、そもそも、「サロメ」のドラマをテクストの台詞に即しながら映像として組み立てて提示するという通常の映画のやり方そのものを、七里監督は大胆不敵にもきっぱり斥けてしまっている。そして、日夏独特の訳文は忠実に生かしつつも、台詞を適宜取捨選択し、ボイス・パフォーマーたちの熱演と音楽・音響デザイン担当の池田拓実の力業のサウンド・ミックスによって一段と様式化を施された原作の対話劇が、背後で繰り広げられる一方、海辺の波や空、大地、夕陽といった無人の風景が、黒画面による長いインターバルを間に挟みつつ断続的にスクリーンに映し出される形で、本作は並列的に進行していく。それらは一見、『眠り姫』の中で映し出される無人の光景と相似ているが、物語の内容と即かず離れずの微妙な距離を保ち、ぼんやりとした不安を抱えたヒロインの心象風景として受け止める余地のある同作のそれに比べると、『映画としての音楽』の中の無人の風景ショットは、ドラマの流れや登場人物との結びつきがきわめて稀薄で、映像の非物語化・非人称化の度合いが一層進んでいる。
(以上、『映画としての音楽』パンフレットより。つづきは、パンフレットでお楽しみ下さい)